解説 お江戸の科学
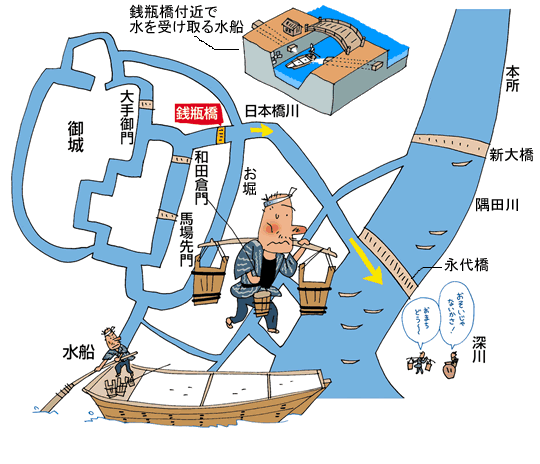
水屋と水船
「水道(すいど)の水で産湯を使い…」は江戸っ子自慢の台詞であったが、この水道が直接届かなかったのが、本所や深川など隅田川の対岸地域。ここに水を運んだのが「水屋」と「水船」である。上水の余り水は、江戸城のお堀に近い銭瓶橋(ぜにかめばし)付近から放出された。その水を、幕府の許可を得て水船で受け、日本橋川を通って隅田川の対岸まで運んだ。
この水を桶に汲み、天秤棒で担いで各家庭に売り歩いたのが、落語に登場した「水屋」という職業。一荷(いっか)(=二桶)で四文。かけそば一杯十六文の時代、責任が重いわりに利益は薄かった。