ふしぎのトビラ 〜 ふるさとサイエンス
TBC東北放送制作、東北地方及び新潟の7局で放送される「ふしぎのトビラ 〜ふるさとサイエンス」に佐藤研究員が出演中です。この番組は、東北地方を中心に地元の不思議を科学するサイエンス番組です。ミッキー先生(佐藤研究員)は、スタジオの子どもたちに実際の実験で、科学をわかりやすく解説します。
月1回放送されています。詳しい放送時間と放送局は、下記ホームページをご参照ください。
番組ホームページは
http://www.tbc-sendai.co.jp/03tv/fushigi/index.html
2007年に放送された番組内容をご紹介します。最新の放送分はこちらです。
 |
 |
 |
 |
 |
 |
12/8放送
気が付けば、はや師走。今月のテーマは、秋田の大太鼓に関連して、音の実験をしました。
一つめの実験は、音の正体である空気の振動を光を利用して目で確かめる実験です。紙コップの底を切り抜いてラップをピンと張り、その中央に小さな鏡を取り付けます。コップに向かって声を出すと空気が震え、ラップが震え、鏡も震えます。この鏡にレーザーの光を当てると、反射したレーザー光は3mほど離れたホワイトボードに投影されます。声を出すと、投影されたレーザーの光の点も震えるわけです。音程を変えて声をだすと、光の点が輪を描くように震えたり、左右に線を描くように震えたりいろいろな形になり、音によってちがう絵が描かれます。
もし、この光から元の音を再現できれば、光で音を運んだことになります。これが、まさに光通信です。次はこの実験にチャレンジしました。
ホワイトボードの上に太陽電池を取り付け、太陽電池のコードはカラオケ機能のあるラジカセのマイク端子に差し込みます。この太陽電池を狙って声で震わせた光をあてます。つまり、太陽電池を光のマイクにしようという試みです。光の当たった太陽電池は、光の震えにそって電圧の強弱が変化します。それがラジカセを通して音として再現されるのです。メリーさんの羊を歌うと、見事に声として再生されました。レーザーポインタの反射光でも懐中電灯でも、ちゃんと音は再生できましたが、音としては懐中電灯のほうがよい結果でした。子どもたちには、はしのえみさんのゴジラの歌がうけていました。 今回はダイレクトに光を飛ばしましたが、光ファイバーを利用すれば、世の中で使われている実用的な光通信により近くなるわけです。
一つめの実験は、音の正体である空気の振動を光を利用して目で確かめる実験です。紙コップの底を切り抜いてラップをピンと張り、その中央に小さな鏡を取り付けます。コップに向かって声を出すと空気が震え、ラップが震え、鏡も震えます。この鏡にレーザーの光を当てると、反射したレーザー光は3mほど離れたホワイトボードに投影されます。声を出すと、投影されたレーザーの光の点も震えるわけです。音程を変えて声をだすと、光の点が輪を描くように震えたり、左右に線を描くように震えたりいろいろな形になり、音によってちがう絵が描かれます。
もし、この光から元の音を再現できれば、光で音を運んだことになります。これが、まさに光通信です。次はこの実験にチャレンジしました。
ホワイトボードの上に太陽電池を取り付け、太陽電池のコードはカラオケ機能のあるラジカセのマイク端子に差し込みます。この太陽電池を狙って声で震わせた光をあてます。つまり、太陽電池を光のマイクにしようという試みです。光の当たった太陽電池は、光の震えにそって電圧の強弱が変化します。それがラジカセを通して音として再現されるのです。メリーさんの羊を歌うと、見事に声として再生されました。レーザーポインタの反射光でも懐中電灯でも、ちゃんと音は再生できましたが、音としては懐中電灯のほうがよい結果でした。子どもたちには、はしのえみさんのゴジラの歌がうけていました。 今回はダイレクトに光を飛ばしましたが、光ファイバーを利用すれば、世の中で使われている実用的な光通信により近くなるわけです。
 |
 |
 |
 |
 |
 |
11/10放送
今月のふしぎのひとつは、コウモリが超音波を出し、その反射音をきいて障害物を察知したり獲物を見つけたりしているということでした。
これに関連して、今月は、音の反射と集中を利用して、音のパワーを感じてもらう実験を行いました。
大きな中華なべを2つ垂直に立て、写真のように1.2mほど離して向かい合わせにたてました。音源は、運動会で目にするスターターピストル、つまり火薬の爆発音です。
1つ目の実験は、中華なべを凹面鏡に見立ててその焦点となる位置に炭酸飲料の入ったコップをおき、もうひとつの中華なべの焦点となる位置でスターターピストルを鳴らします。音を鳴らすとほぼ同時にコップから泡が一斉に発生しました。火薬の爆発による衝撃音が中華なべで反射し、もう一方の中華なべに達し、そこでまた反射して焦点に集まって、そこにあった炭酸飲料に刺激を与えたのです。
もう1つの実験では、ろうそくを1列に5本ならべて火をつけ、同じようにスターターで音を発生させました。結果は、5本のうち1番中華なべに近い、なべの焦点の位置にあるった炎だけが消えました。音は空気の震えです。音が集中したところは、衝撃的な強い音になり、瞬間的に強烈に空気が震えます。その強烈な震えが火を消したのです。瞬間的に息でフッと吹き消した感じに近いと思います。音の集まらない他のろうそくの炎は消えません。この実験は、前日本物理教育学会副会長の大山先生に何年も前に教えていただいたものです。
これに関連して、今月は、音の反射と集中を利用して、音のパワーを感じてもらう実験を行いました。
大きな中華なべを2つ垂直に立て、写真のように1.2mほど離して向かい合わせにたてました。音源は、運動会で目にするスターターピストル、つまり火薬の爆発音です。
1つ目の実験は、中華なべを凹面鏡に見立ててその焦点となる位置に炭酸飲料の入ったコップをおき、もうひとつの中華なべの焦点となる位置でスターターピストルを鳴らします。音を鳴らすとほぼ同時にコップから泡が一斉に発生しました。火薬の爆発による衝撃音が中華なべで反射し、もう一方の中華なべに達し、そこでまた反射して焦点に集まって、そこにあった炭酸飲料に刺激を与えたのです。
もう1つの実験では、ろうそくを1列に5本ならべて火をつけ、同じようにスターターで音を発生させました。結果は、5本のうち1番中華なべに近い、なべの焦点の位置にあるった炎だけが消えました。音は空気の震えです。音が集中したところは、衝撃的な強い音になり、瞬間的に強烈に空気が震えます。その強烈な震えが火を消したのです。瞬間的に息でフッと吹き消した感じに近いと思います。音の集まらない他のろうそくの炎は消えません。この実験は、前日本物理教育学会副会長の大山先生に何年も前に教えていただいたものです。
 |
 |
 |
 |
 |
 |
10/13放送
今月は、番組で「貝塚」を取り上げたので、それに関連してホタテガイの殻を使った実験を行いました。
仙台の名物駅弁「牛タン弁当」には、紐をひっぱると湯気が出て弁当が暖まる仕掛けがついています。これは化学反応による熱で、それを実験で確かめました。
まずホタテガイの殻を、1000度くらいの熱でガンガン加熱します。すると貝殻は白くてもろいものになります。貝殻は主に炭酸カルシウムでできています。それが高熱で酸化カルシウム、いわゆる生石灰に変化したのです。これを冷ましてすり鉢ですり、粉にします。これが発熱のための材料になります。
粉をビニール袋に入れて、スポイトで水をたらします。すると徐々に熱くなっていき、蒸気がどんどん発生し、ついには袋の一部がとけて外に粉がこぼれてしまいました。生石灰が水酸化カルシウム、酸性の畑の中和剤に使われる消石灰に変化したのです。この変化するときに大量の熱を発生するのです。消石灰は、水に溶けると比較的強いアルカリ性になるので扱いには注意が必要です。
ミニ玉子焼き作りにも挑戦しました。カップに粉を多めに入れて水をたらし、その上にホイルカップに入れた卵をおきました。粉の中の温度は200度以上もあり、子どもたちはびっくりでした。牛タン弁当もまったく同じ原理で熱を発生させています。科学反応には熱の出入りがつきものですが、身近なものを使ってこれほど驚くような反応はなかなか見られません。ちなみに携帯用のカイロも鉄と水分が反応して熱を出す、化学反応を利用しています。
仙台の名物駅弁「牛タン弁当」には、紐をひっぱると湯気が出て弁当が暖まる仕掛けがついています。これは化学反応による熱で、それを実験で確かめました。
まずホタテガイの殻を、1000度くらいの熱でガンガン加熱します。すると貝殻は白くてもろいものになります。貝殻は主に炭酸カルシウムでできています。それが高熱で酸化カルシウム、いわゆる生石灰に変化したのです。これを冷ましてすり鉢ですり、粉にします。これが発熱のための材料になります。
粉をビニール袋に入れて、スポイトで水をたらします。すると徐々に熱くなっていき、蒸気がどんどん発生し、ついには袋の一部がとけて外に粉がこぼれてしまいました。生石灰が水酸化カルシウム、酸性の畑の中和剤に使われる消石灰に変化したのです。この変化するときに大量の熱を発生するのです。消石灰は、水に溶けると比較的強いアルカリ性になるので扱いには注意が必要です。
ミニ玉子焼き作りにも挑戦しました。カップに粉を多めに入れて水をたらし、その上にホイルカップに入れた卵をおきました。粉の中の温度は200度以上もあり、子どもたちはびっくりでした。牛タン弁当もまったく同じ原理で熱を発生させています。科学反応には熱の出入りがつきものですが、身近なものを使ってこれほど驚くような反応はなかなか見られません。ちなみに携帯用のカイロも鉄と水分が反応して熱を出す、化学反応を利用しています。
 |
 |
 |
 |
 |
 |
09/08放送
9月のテーマ、紅花染め関連して色の変化の不思議を楽しむ2つの実験を行いました。
一つめの実験は「消える紫」。薄紫の透明な水をストローでぶくぶく息を吹き込むと10秒ほどで、すっと色が消え、無色の水になってしまいます。使っているのは「フェノールフタレイン」という薬品で、アルカリ性では赤紫、酸性では無色になる検査薬です。息には二酸化炭素が多く含まれ、それが水に溶けると弱い酸性になります。それで無色になったのです。ちょっとした魔法の水です。
次に紹介したのは「電気ペン」の実験。
トレー全体にアルミホイルを、その上にキッチンペーパーを敷きます。電池2本を直列につなぎ、アルミホイルを細く折ってリード線を作り、プラス極はアルミホイルに、マイナス極はスプーンにつなげます。キッチンペーパーに濃い食塩水を流れない程度にたっぷり含ませ、その上全体にカレー粉を茶漉しで薄く均等にまきます。そしてスプーンをペンのようにして、カレー粉の上をゆっくりなぞっていくと…見る見る黄色のカレー粉が赤に変わり、絵が描かれていきます。これはアルミホイルスプーンの間に電気が流れることで、スプーンの周辺で化学反応が起こり、食塩水がアルカリ性の水溶液になったからです。つまりOH-(水酸化物イオン)が集まったのです。カレー粉の黄色はターメリックという粉で、これに含まれる黄色の色素ークルクミンはアルカリ性では赤く変色します。スプーンの周辺だけがアルカリ性になったので赤い線が描けたのです。
色は酸性かアルカリ性かで変化することがよくあります。紫キャベツや紅茶のマローブルーなどで色水をつくり、酸性の酢やレモン、アルカリ性の重曹などを使って、濃さや量を変えながら色変わりの実験してみるのも楽しいですよ。
一つめの実験は「消える紫」。薄紫の透明な水をストローでぶくぶく息を吹き込むと10秒ほどで、すっと色が消え、無色の水になってしまいます。使っているのは「フェノールフタレイン」という薬品で、アルカリ性では赤紫、酸性では無色になる検査薬です。息には二酸化炭素が多く含まれ、それが水に溶けると弱い酸性になります。それで無色になったのです。ちょっとした魔法の水です。
次に紹介したのは「電気ペン」の実験。
トレー全体にアルミホイルを、その上にキッチンペーパーを敷きます。電池2本を直列につなぎ、アルミホイルを細く折ってリード線を作り、プラス極はアルミホイルに、マイナス極はスプーンにつなげます。キッチンペーパーに濃い食塩水を流れない程度にたっぷり含ませ、その上全体にカレー粉を茶漉しで薄く均等にまきます。そしてスプーンをペンのようにして、カレー粉の上をゆっくりなぞっていくと…見る見る黄色のカレー粉が赤に変わり、絵が描かれていきます。これはアルミホイルスプーンの間に電気が流れることで、スプーンの周辺で化学反応が起こり、食塩水がアルカリ性の水溶液になったからです。つまりOH-(水酸化物イオン)が集まったのです。カレー粉の黄色はターメリックという粉で、これに含まれる黄色の色素ークルクミンはアルカリ性では赤く変色します。スプーンの周辺だけがアルカリ性になったので赤い線が描けたのです。
色は酸性かアルカリ性かで変化することがよくあります。紫キャベツや紅茶のマローブルーなどで色水をつくり、酸性の酢やレモン、アルカリ性の重曹などを使って、濃さや量を変えながら色変わりの実験してみるのも楽しいですよ。
 |
 |
 |
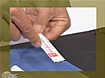 |
 |
 |
08/11放送
今月は蒸気機関車はなぜ動くのか、その力の源が何かを探った内容だったので、実験は水蒸気を使ったものを紹介しました。
水を熱すると水蒸気になります。そのとき体積は1600倍以上になり、閉じた容器の中では非常に高い圧力を生み出します。この蒸気パワーを利用した2つの実験を紹介しました。
一つ目は、約2000年前のへロンという古代ギリシャ人が考えたといわれる、蒸気タービンと同じ原理で動く、身近なものを使った実験です。フタつきの缶コーヒーを用意し、本体の上部に千枚通しで小さな、少し横向きの穴をあけます。フタを小さなネオジウム磁石とクリップではさみ、磁力でつり下げられるようにします。2〜3ccの水を入れて固形燃料で熱すると、小さな穴から水蒸気が噴き出し、コーヒー缶が回転し始めます。かなりの速度で回る、シンプルですがおもしろい実験です。
もう一つは、ポンポン蒸気船の再現工作です。マジックインクの金属の柄の部分を使います。両はしに竹串などを差し込んでつぶれないようにしながら、プライヤーなどでつぶしていきます。結果、Uの字のパイプのような水の通り道ができます。これを蚊取り線香の金属台につけ、発泡スチロールの容器に貼り付けます。スポイトでマジックの柄の中に水を入れ、先端部分をロウソクで熱します。しばらくすると、船は水面に小さな波紋を作りながら、ゆっくりと進み始めます。実は、マジックの柄の先はボイラーの役目をしています。反対側は、水中に少し入っています。ボイラーの中で水蒸気がだんだん発生し、十分に熱せられると爆発的に蒸気が噴き出て、勢い良く水を押し出します。このときの力が推進力になります。直後、ボイラーの中は圧力が弱くなるため、外の水を吸い込みます。そしてまた熱せられ…と、素早く何度も繰り返されます。これを自励振動といいます。シンプルな構造ですが、熱するだけで震えながら進むようすが、とても不思議に感じられる実験でした。
水を熱すると水蒸気になります。そのとき体積は1600倍以上になり、閉じた容器の中では非常に高い圧力を生み出します。この蒸気パワーを利用した2つの実験を紹介しました。
一つ目は、約2000年前のへロンという古代ギリシャ人が考えたといわれる、蒸気タービンと同じ原理で動く、身近なものを使った実験です。フタつきの缶コーヒーを用意し、本体の上部に千枚通しで小さな、少し横向きの穴をあけます。フタを小さなネオジウム磁石とクリップではさみ、磁力でつり下げられるようにします。2〜3ccの水を入れて固形燃料で熱すると、小さな穴から水蒸気が噴き出し、コーヒー缶が回転し始めます。かなりの速度で回る、シンプルですがおもしろい実験です。
もう一つは、ポンポン蒸気船の再現工作です。マジックインクの金属の柄の部分を使います。両はしに竹串などを差し込んでつぶれないようにしながら、プライヤーなどでつぶしていきます。結果、Uの字のパイプのような水の通り道ができます。これを蚊取り線香の金属台につけ、発泡スチロールの容器に貼り付けます。スポイトでマジックの柄の中に水を入れ、先端部分をロウソクで熱します。しばらくすると、船は水面に小さな波紋を作りながら、ゆっくりと進み始めます。実は、マジックの柄の先はボイラーの役目をしています。反対側は、水中に少し入っています。ボイラーの中で水蒸気がだんだん発生し、十分に熱せられると爆発的に蒸気が噴き出て、勢い良く水を押し出します。このときの力が推進力になります。直後、ボイラーの中は圧力が弱くなるため、外の水を吸い込みます。そしてまた熱せられ…と、素早く何度も繰り返されます。これを自励振動といいます。シンプルな構造ですが、熱するだけで震えながら進むようすが、とても不思議に感じられる実験でした。
 |
 |
 |
 |
 |
 |
07/14放送
今月は、どうして鉄でできた船が浮かぶのかという、とても素朴な疑問がテーマにでした。そこで浮力の実験を行いました。
一つめの実験。まずペットボトルの上を切り取り、長いコップのような形にします。金魚を飼うときに使うエアーストーンを容器の底に入れて、さらにチューブをつなぎ、容器に水を入れます。チューブに息を吹き込むとたくさんの泡が出てきます。直径が4cmほどのスーパーボールを入れると、水より少し軽いので浮きます。ここでクイズ。息を吹き込んだらボールはどうなる?空気が泡になってスーパーボールの下をたたくのだから、ボールは浮くように思えます。しかし実験してみると逆に沈んでしまいます。理由は、たくさんの泡が水の中に広がることで、水全体がスカスカになってしまうのです。スカスカの水は普通の水よりも軽いので、相対的にボールの方が重くなります。それで沈んだのです。バミューダ海域での船が突然消滅する現象が世界の7不思議にありますが、その理由の一つに海底からのガスの泡による沈没という説があります。この実験のボールが船という考え方です。
もう一つは、コップの中にピンポン玉を入れ、その上にお米を一杯に入れます。そしてマッサージ器をコップの底にあて振動を与えます。すると、お米の粒がプルプル震えながらゆっくりと移動します。すると、閉じ込められていたピンポン玉がお米の上に浮かび上がります。お米の粒一つ一つを水の分子に見立てた実験です。振動させる前は水の分子が移動できない氷の状態で、振動によって動き出したときが液体の状態なのです。浮力が働くときの水の分子の動きをイメージしてもらえましたか?
一つめの実験。まずペットボトルの上を切り取り、長いコップのような形にします。金魚を飼うときに使うエアーストーンを容器の底に入れて、さらにチューブをつなぎ、容器に水を入れます。チューブに息を吹き込むとたくさんの泡が出てきます。直径が4cmほどのスーパーボールを入れると、水より少し軽いので浮きます。ここでクイズ。息を吹き込んだらボールはどうなる?空気が泡になってスーパーボールの下をたたくのだから、ボールは浮くように思えます。しかし実験してみると逆に沈んでしまいます。理由は、たくさんの泡が水の中に広がることで、水全体がスカスカになってしまうのです。スカスカの水は普通の水よりも軽いので、相対的にボールの方が重くなります。それで沈んだのです。バミューダ海域での船が突然消滅する現象が世界の7不思議にありますが、その理由の一つに海底からのガスの泡による沈没という説があります。この実験のボールが船という考え方です。
もう一つは、コップの中にピンポン玉を入れ、その上にお米を一杯に入れます。そしてマッサージ器をコップの底にあて振動を与えます。すると、お米の粒がプルプル震えながらゆっくりと移動します。すると、閉じ込められていたピンポン玉がお米の上に浮かび上がります。お米の粒一つ一つを水の分子に見立てた実験です。振動させる前は水の分子が移動できない氷の状態で、振動によって動き出したときが液体の状態なのです。浮力が働くときの水の分子の動きをイメージしてもらえましたか?
 |
 |
 |
 |
 |
 |
06/09放送
今回は鉄の特長がテーマということで、磁石を使った実験をしました。
多くの金属の中で、磁石につくのは、鉄とニッケル、コバルトくらいですから、磁石につくことを鉄の大きな特徴としてあげてもよいでしょう。
一つめの実験は、スプーン磁石。鉄のスプーンを磁石につけると、スプーンは磁化して弱い磁石になり、鉄のクリップ持ち上げることができます。次に、スプーンをレンガに勢いよく何度もたたきつけます。するとクリップがつかなくなります。実はスプーン、つまり鉄はミニ磁石の集まりだからです。普段はそのミニ磁石の向きがばらばらなので、全体として磁石にはなっていません。ところがいったん磁石につけると、ミニ磁石が整列します。磁石からはなすと、ミニ磁石の向きがばらばらになりますが、ある程度は整列したものが残ります。そのために弱い磁石として働きます。これに強い衝撃を与えると、完全に向きがばらばらになるために、磁力をなくすというわけです。
もう一つは、電磁石の実験です。直径3cm、高さが2cmほどの円柱の鉄のまわりに、コイルをつけて電磁石を作りました。クリップなどがつくくらいの、とても弱い磁石です。この弱い磁石を厚さ4mmほどの鉄で囲みます。すると、人もぶら下がれるくらいの強力な磁石になりました。約130kgまで大丈夫で、実際に107kgの人がぶら下がりましたがびくともしませんでした。鉄の囲いがないと、磁力が広がって逃げてしまいます。しかし磁力は鉄の中を通りやすく、囲いの鉄の中を密度たかく集中して通るので、効率よく働くのです。またN極とS極がとても近い構造になるため、すごい力を発揮したのです。
多くの金属の中で、磁石につくのは、鉄とニッケル、コバルトくらいですから、磁石につくことを鉄の大きな特徴としてあげてもよいでしょう。
一つめの実験は、スプーン磁石。鉄のスプーンを磁石につけると、スプーンは磁化して弱い磁石になり、鉄のクリップ持ち上げることができます。次に、スプーンをレンガに勢いよく何度もたたきつけます。するとクリップがつかなくなります。実はスプーン、つまり鉄はミニ磁石の集まりだからです。普段はそのミニ磁石の向きがばらばらなので、全体として磁石にはなっていません。ところがいったん磁石につけると、ミニ磁石が整列します。磁石からはなすと、ミニ磁石の向きがばらばらになりますが、ある程度は整列したものが残ります。そのために弱い磁石として働きます。これに強い衝撃を与えると、完全に向きがばらばらになるために、磁力をなくすというわけです。
もう一つは、電磁石の実験です。直径3cm、高さが2cmほどの円柱の鉄のまわりに、コイルをつけて電磁石を作りました。クリップなどがつくくらいの、とても弱い磁石です。この弱い磁石を厚さ4mmほどの鉄で囲みます。すると、人もぶら下がれるくらいの強力な磁石になりました。約130kgまで大丈夫で、実際に107kgの人がぶら下がりましたがびくともしませんでした。鉄の囲いがないと、磁力が広がって逃げてしまいます。しかし磁力は鉄の中を通りやすく、囲いの鉄の中を密度たかく集中して通るので、効率よく働くのです。またN極とS極がとても近い構造になるため、すごい力を発揮したのです。
 |
 |
 |
 |
 |
 |
05/12放送
5月といえば、潮干狩りの季節。潮干狩りは潮の干満の差が大きい大潮の日がもってこいですね。番組では潮の干満に、月や太陽の引力が大きな影響を与えていることを紹介しました。それに関連して万有引力についての実験をしました。ものが落ちるのは、地球と物体の間に働く万有引力のせいです。重い鉄球と鳥の羽を同時に落とすと、当然鉄球のほうが早く地面に着きます。しかし、空気抵抗がなく引力だけが働く世界では、鳥の羽も鉄球も同じ速度で落ちるのです。鉄と鳥の羽が同時に落ちる姿を想像できますか?ということで、今回は高さ60cmの真空実験用容器を作って実際に確かめました。ホッチキスの針を2ミリほど切り取り鳥の羽につけて磁石につくようにし、容器の蓋をはさんで磁石で鉄球と鳥の羽をぶら下げました。
まず、空気中で羽と鉄球の落ち方の違いをしっかり見てもらいました。続いて、真空容器の磁石を外すと、磁力が届かなくなった瞬間に鉄球と羽は落ち始めました。そして一瞬でしたが、ほぼ同じ速さで落ちました。日常目にすることとまったく違ったことが目の前で起こると、とてもびっくりします。空気の抵抗がほとんどない空間では、このように物体の大きさや重さに関係なく同じ速度で落ちるのです。月には空気(気体)がありません。ですから、月でも羽と鉄球の落下実験は同じ結果になるはずです。ただし、月の重力は地球の6分の1ですから、落ちるスピードは遅くなります。
せっかく真空実験装置があるので、中に目覚まし時計を入れて鳴らしてみました。音を伝える空気がないので音は聞こえません。目の前にあるのに音が聞こえないのはとても不思議な感じです。実際は、わずかに空気が残っていたので、かすかに音はもれていましたが。空気を入れるとずっと大きな音が外に伝わってきました。
まず、空気中で羽と鉄球の落ち方の違いをしっかり見てもらいました。続いて、真空容器の磁石を外すと、磁力が届かなくなった瞬間に鉄球と羽は落ち始めました。そして一瞬でしたが、ほぼ同じ速さで落ちました。日常目にすることとまったく違ったことが目の前で起こると、とてもびっくりします。空気の抵抗がほとんどない空間では、このように物体の大きさや重さに関係なく同じ速度で落ちるのです。月には空気(気体)がありません。ですから、月でも羽と鉄球の落下実験は同じ結果になるはずです。ただし、月の重力は地球の6分の1ですから、落ちるスピードは遅くなります。
せっかく真空実験装置があるので、中に目覚まし時計を入れて鳴らしてみました。音を伝える空気がないので音は聞こえません。目の前にあるのに音が聞こえないのはとても不思議な感じです。実際は、わずかに空気が残っていたので、かすかに音はもれていましたが。空気を入れるとずっと大きな音が外に伝わってきました。
 |
 |
 |
 |
 |
 |
04/14放送
今回は、番組で紹介した津軽凧に関連して、ちょっと変わった凧の実験 です。
「マグナスの凧」という珍しい凧を紹介しました。これは薄い発泡スチロールの板をS字状に曲げて羽を作り、その羽が風を受けて回転することで揚力を得る凧です。
凧を横から見たとき羽が右回りに回ると、その円周にそって羽の動きと同じように右回りの空気の流れが起こります。風が右に向かって流れている場合、回転する凧の上側では風の方向と右回り空気の流れの向きが同じなので、早い速度で空気が流れることになります。空気の流れが速いところは、圧力が小さくなります。反対に下側では、風の向きと回る風の向きが逆になるので、お互い勢いを殺し合って空気の流れは遅くなり、圧力が大きくなります。その結果、凧の上下で圧力差が生じることになります。その差が凧を持ち上げる力、つまり「揚力」になるわけです。
このように、回転するものに風があたると回転の軸に対して直角方向に力が発生します。これを「マグナス効果」といいます。それで、この凧を「マグナスの凧」と呼んでいるのです。
そのほか、弱い風でもあがるとても簡単な凧も紹介しました。
「マグナスの凧」という珍しい凧を紹介しました。これは薄い発泡スチロールの板をS字状に曲げて羽を作り、その羽が風を受けて回転することで揚力を得る凧です。
凧を横から見たとき羽が右回りに回ると、その円周にそって羽の動きと同じように右回りの空気の流れが起こります。風が右に向かって流れている場合、回転する凧の上側では風の方向と右回り空気の流れの向きが同じなので、早い速度で空気が流れることになります。空気の流れが速いところは、圧力が小さくなります。反対に下側では、風の向きと回る風の向きが逆になるので、お互い勢いを殺し合って空気の流れは遅くなり、圧力が大きくなります。その結果、凧の上下で圧力差が生じることになります。その差が凧を持ち上げる力、つまり「揚力」になるわけです。
このように、回転するものに風があたると回転の軸に対して直角方向に力が発生します。これを「マグナス効果」といいます。それで、この凧を「マグナスの凧」と呼んでいるのです。
そのほか、弱い風でもあがるとても簡単な凧も紹介しました。
 |
 |
 |
 |
03/10放送
今回は2006年度の締めくくりということで、1時間の特番となり、2つの実験を紹介しました。
一つは、こぼれないお盆です。お盆に3本のひもをつけて指でつるし、振り子のように自由にゆれる状態にします。このお盆の真ん中にお湯をいれた湯飲みをおきます。これを使ってウェイトレスをやってみる実験です。お盆は相当ゆれるのに、水面は鏡のようにピタッと止まってゆれません。なぜでしょう。お盆は常に力がかかる方向にぶら下がっている状態なのです。目には動いているように見えますが、瞬間で考えると斜めになっているときでもお盆はぶら下がっているときと同じ状態なのです。それで、水面も動かないわけです。ちょっと難しいですけどね…。おそば屋さんの配達のバイクには、つゆがこぼれない工夫がありますが、これと同じ原理を使っています。
一つは、こぼれないお盆です。お盆に3本のひもをつけて指でつるし、振り子のように自由にゆれる状態にします。このお盆の真ん中にお湯をいれた湯飲みをおきます。これを使ってウェイトレスをやってみる実験です。お盆は相当ゆれるのに、水面は鏡のようにピタッと止まってゆれません。なぜでしょう。お盆は常に力がかかる方向にぶら下がっている状態なのです。目には動いているように見えますが、瞬間で考えると斜めになっているときでもお盆はぶら下がっているときと同じ状態なのです。それで、水面も動かないわけです。ちょっと難しいですけどね…。おそば屋さんの配達のバイクには、つゆがこぼれない工夫がありますが、これと同じ原理を使っています。
 |
 |
 |
 |
もう1つは、モンキーハンティング。それは…ハンターが木にぶら下がっているサルを鉄砲で狙いをつけて撃つと、その音にびっくりしてサルが落ちます。落ちれば弾は当たらなそうですが、サルは落ちていく途中で必ず弾があたるという不思議な実験です。 ハンターから4〜5mほど離れたところで、高さ3mくらいでボールを持ってもらいます。おもちゃの鉄砲で正確にボールをねらいって弾を発射し、発射と同時にボールを離してもらいます。ボールは自然に落ちていきますが、なんと1mほど落ちたところで弾がボールに当たります。原理を説明するのはちょっと難しいのですが、正確に狙って弾の発射とボールをはなすのが同時であれば、何度やっても当たってしまうです。ボールも弾も同じ時間に同じ距離だけ落ちるという実験なのです。
 |
 |
 |
 |
 |
 |
02/10放送
今月は、テーマの一つである「摩擦」に関する実験を紹介しました。
一つめは、「指は真ん中を知ってるぜ!実験」。長さ60cm の丸棒を用意します。左右の手を50cmほど離し、両方の人差し指 で棒を下から支えます。そして指をゆっくり近づけていき、人差し指が くっつくまで動かします。するとだれがやっても、棒は落ちそうになり ながらも落ちず、最後には左右の指が棒の中心でくっつくのです。進行 役のTAKE2の深沢さんが、中心以外の場所で指がくっつくように 努力しても、必ず棒の中心で出会うのです。なぜでしょうか?左右の指 には棒の重さがかかっていますが、かかる重さには違いができます。指 を動かそうとすると軽く感じている指の方が棒との摩擦が小さいため動 き出します。そうしてあるところまで来ると、もう一方の指の方が軽く なるため摩擦が小さくなって、その指が内側に動きます。結果、交互に 指が動いてほぼ中心で出会います。子供たちに実際にやってもらいまし たが、この不思議にとても喜んでくれました。
もう一つは、CD-Rとフィルムケース、風船を使ったホバークラフ ト工作。風船から吹き出す空気がCD-Rとテーブルの間にごくわず かな空気の層を作るため、摩擦がとても小さくなり、本物のホバークラ フトのようにスーッとすべるのです。
一つめは、「指は真ん中を知ってるぜ!実験」。長さ60cm の丸棒を用意します。左右の手を50cmほど離し、両方の人差し指 で棒を下から支えます。そして指をゆっくり近づけていき、人差し指が くっつくまで動かします。するとだれがやっても、棒は落ちそうになり ながらも落ちず、最後には左右の指が棒の中心でくっつくのです。進行 役のTAKE2の深沢さんが、中心以外の場所で指がくっつくように 努力しても、必ず棒の中心で出会うのです。なぜでしょうか?左右の指 には棒の重さがかかっていますが、かかる重さには違いができます。指 を動かそうとすると軽く感じている指の方が棒との摩擦が小さいため動 き出します。そうしてあるところまで来ると、もう一方の指の方が軽く なるため摩擦が小さくなって、その指が内側に動きます。結果、交互に 指が動いてほぼ中心で出会います。子供たちに実際にやってもらいまし たが、この不思議にとても喜んでくれました。
もう一つは、CD-Rとフィルムケース、風船を使ったホバークラフ ト工作。風船から吹き出す空気がCD-Rとテーブルの間にごくわず かな空気の層を作るため、摩擦がとても小さくなり、本物のホバークラ フトのようにスーッとすべるのです。
 |
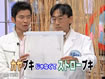 |
 |
 |
01/13放送
茅葺き屋根の雨がなぜ漏れてこないかを説明するために、ストローを使った実験を行いました。茅葺き屋根には、ヨシ(正しくはアシ)がよく使われます。ヨシは高さ3mにもなる湿地に生える植物で、茎の表面が緻密で水が非常にしみこみにくいのが特徴です。ストローも水を吸い込まず、細く長いので、これを使ってストローふき屋根を作りました。説明のために、一層ずつ重ねられるように3層作りました。また、ストローは1〜2ミリ間隔でならべ、隙間を作りました。
まず1層を水平にして水をかけます。当然、隙間からどんどん水が漏れてきます。斜め約45度に傾けると、漏れてはきますが、かなりの水がストローをつたって流れていきます。水は、超撥水性のものをのぞいて物に沿って流れます。これを、水のものに対する付着力といいます。3層にするとほとんど水が漏れてきません。たくさんのストローに沿い、隙間を通った水のほとんどが外に逃げていくからです。
茅葺き屋根は、自然の素材をうまく利用した先人の知恵ですね。
まず1層を水平にして水をかけます。当然、隙間からどんどん水が漏れてきます。斜め約45度に傾けると、漏れてはきますが、かなりの水がストローをつたって流れていきます。水は、超撥水性のものをのぞいて物に沿って流れます。これを、水のものに対する付着力といいます。3層にするとほとんど水が漏れてきません。たくさんのストローに沿い、隙間を通った水のほとんどが外に逃げていくからです。
茅葺き屋根は、自然の素材をうまく利用した先人の知恵ですね。