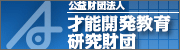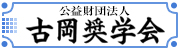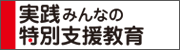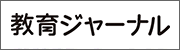- 2012年7月調査
- 2011年12月調査
- 2011年6月調査
- 2010年9月調査
渡辺恵(明治学院大学非常勤講師)
1.家庭におけるしつけ・教育の方針
1990年代以降、幼児期・学童期に活用できる民間の学校外教育が発展したこともあり、語学や音楽、絵画、自然体験、スポーツ、環境を守る活動や国際交流などの社会参加活動など、子どもが経験できる事柄が多種多様になってきている。こうした教育環境の変化は、子どもの教育に関わる数多くの選択肢を家庭にもたらすこととなった。それは、子育てにおいて何を重視するのか、どのような教育を子どもに与えるのかなど、しつけや教育に対する保護者の構えが今まで以上に問われることにもつながる。そこで、この節では、実際に、小学6年生の子どもを持つ家庭が子どものしつけや教育に対してどのような方針をとっているのかをみていくことにする。
(1)日常生活に関わるしつけの方針
はじめに、日常生活に関わるしつけに関わる家庭の構えを見ていこう。図2-1は、子どもに基本的な生活能力を獲得させるための働きかけをどの程度心がけているのかを尋ねた結果である。
図2-1.しつけに対する家庭の方針(全体、出生順位・性別 単位:%)
*「とてもあてはまる」と「まああてはまる」の合計の割合
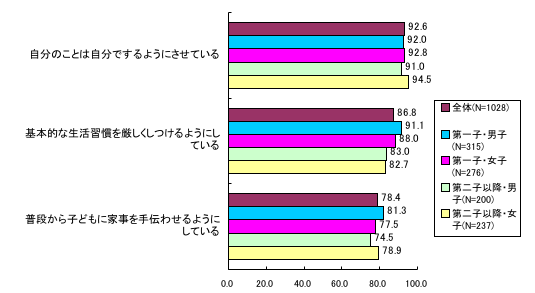
全体をみると、「自分のことは自分でするようにさせている」では約9割の家庭が「あてはまる」(「とてもあてはまる」と「まああてはまる」の合計)と回答している。どの家庭でも「自分のことは自分でするように」しつけていることがわかる。また、「基本的な生活習慣を厳しくしつけている」家庭が8割強、「普段から子どもに家事を手伝わせている」家庭が8割弱である。ほとんどの家庭が子どもの基本的な生活能力を高める働きかけを心がけていることがわかる。
子どもの性別・出生順位ごとに着目してみよう。「基本的な生活習慣を厳しくしつけるようにしている」と「普段から子どもに家事を手伝わせるようにしている」の項目において、多少の相違が見て取れる。「基本的な生活習慣を厳しくしつける」ことでは、「第一子・男子」(「とてもあてはまる」と「まああてはまる」の合計が91.1%)、「第一子・女子」(同88.0%)、「第二子以降・男子」(同83.0%)、「第二子以降・女子」(同82.7%)の順で割合が高くなっている。「第一子」に比べ、「第二子以降」の子どもに対しては、生活習慣を厳しくしつける傾向が弱まるようである。家事を手伝わせることに関しては、女子では出生順位による違いは見受けられないが、男子では、「第一子」(同81.3%)よりも「第二子以降」(同74.5%)において、働きかけが弱まっている。総じて、第一子の男子に対しては、子どもに生活習慣や生活能力を獲得させるためのしつけを最も強く心がけていることがわかる。第一子では、親は子育てに対する不安を抱えやすいため、生活習慣や生活能力を身につけさせることにより注意を払おうとするのだろう。しかし、第二子以降では、第一子の子育て経験から、どの程度注意を払えばよいのかの加減がわかるためか、しつけがある程度ゆるむと考えられる。
なお、図2-1が示すように、子どもの性別による違いはほとんどみられなかった。これは、家事手伝いを含め、基本的な生活能力を習得させることに関しては、性別役割分業意識が社会的に緩和してきていることを反映しているのではないだろうか。
それでは、どのような家庭が日常生活に関わるしつけを重視する傾向があるのだろうか。この点を、母親の就業形態や教育経験の2点から確認しておこう。表2-1は、母親の就業形態別(1)と最終学歴別にみた結果を示している。就業形態や教育経験を母親のみに限定するのは、しつけに対する家庭の方針が主に面倒をみている人の考えを反映しやすいと考えるためであり、今回の調査では、家族の中で小学6年生の子どもの面倒を主にみている人の約9割が母親であったためである。なお、就業形態が「自営業・自由業(家業手伝い含む)」の数値に関しては、該当する母数が少ないため、結果を読み取る際には注意が必要である。
表2-1.母親の就業形態別と最終学歴別にみた、しつけに対する家庭の方針(単位:%)
*「あてはまる」の合計は「とてもあてはまる」と「まああてはまる」の回答の合計
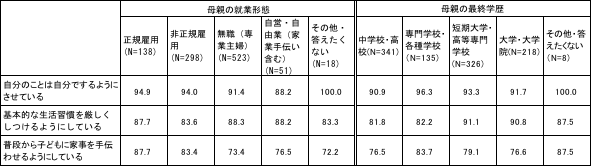
母親の就業形態別に見たときに、次のような特徴が見受けられる。母親が勤めに出ている家庭では、家事手伝いに関するしつけを重視する傾向が強いことである。母親が「正規雇用」で勤めている家庭では、「普段から子どもに家事を手伝わせるようにしている」割合が87.7%、「非正規雇用」では83.6%と、母親が「無職」である家庭に比べ、約10~14ポイントほど高くなっている。参考までに言えば、「自分のことは自分でするようにしている」の項目では、「あてはまる」の合計では差はほとんどみられないが、「とてもあてはまる」の割合に着目すると、「正規雇用」では44.3%であり「非正規雇用」では43.6%であり、母親が「無職」である家庭よりも5~6ポイントほどやはり高くなっている。このことから、母親が働きに出て家を留守にする家庭ほど、家事能力や自分のことは自分で行う力を身につけさせるといった、家庭生活を自立的に行えるように働きかけることを重視していると指摘できよう。
母親の最終学歴別(表2-1参照)に着目すると、次のような特徴が窺える。母親が「専門学校・各種学校卒」である家庭では、家庭生活の能力を身につけさせることをもっとも重視する構えが見て取れることである。「普段から子どもに家事を手伝わせる」ことを心がけている家庭は83.7%であり、唯一8割を超えている。また、「自分のことは自分でするようにさせている」の項目では96.3%の家庭が心がけており、他の家庭に比べ若干高くなっている。母親が「専門学校・各種学校卒」の家庭では、実践的な家事能力の習得を含め、家庭生活に関わる自立を促すことに力を入れていると思われる。
もうひとつは、母親が「短期大学・高等専門学校卒」や「大学・大学院卒」である家庭では、「基本的な生活習慣を厳しくしつける」ことが重視されていることである。母親が「短期大学・高等専門学校卒」や「大学・大学院卒」である家庭では、「専門学校・各種学校卒」や「中学・高校卒」の家庭に比べ8~9ポイントほど高くなっている。基本的な生活習慣の習得は、学校生活への適応にも深く関わっている。その点で、母親が大学機関での教育を受けている家庭では、「専門学校・各種学校卒」の家庭が重視している家庭生活に関わる能力の習得よりも、「基本的な生活習慣」に関わるしつけを行い、学校生活への適応力を高めることにより力を入れているとみることもできよう。
- <注>
- (1) 母親の就業形態の各項目の母数は、母親の仕事について尋ねた結果を次のように再集計したものである。「正規雇用」の母数は母親の職業を尋ねた質問に「民間企業・官公庁・団体などの正社員・正職員」の各職種(「管理職」「専門技術系職員」「販売・サービス・事務系職員」「熟練工・整備士などの技能工」「生産工程・運輸従事者」「その他」)に、「企業、法人・団体等の経営者・役員」を加えた回答数である。「非正規雇用」は「パートタイマー・アルバイト・臨時職員など」の回答数である。「自営・自由業(家業手伝いを含む)」は、「自営業」及び「自由業」、「家族従事者(家業手伝い)」の回答数である。「無職」は「無職(専業主婦を含む)」の回答数である。「その他・答えたくない」は「その他・答えたくない」に「学生(勤労学生を除く)」を加えた回答数である。

-
- »はじめに
- »第1章 保護者の属性から見た子どもの「理科好き」
- はじめに
- 1.子どもの「理科的な活動」への取り組みと「理科好き」
- 2.保護者の職業と子どもの「理科好き」
- 3.保護者の所得と子どもの「理科好き」
- 4.保護者が受けてきた教育と子どもの「理科好き」
- おわりに
- »第2章 子どもの教育に対する家庭の方針 -理科的な活動に対する保護者のかまえに着目して-
- はじめに
- 1.家庭におけるしつけ・教育の方針
- (1)日常生活に関わるしつけの方針
- (2)子どもの学習への関与志向
- (3)子どもの教育達成への期待
- (4)多様な活動経験の提供に対する構え
- 2.理科的な活動に対する保護者の構え
- (1)理系分野に進むことへの期待
- (2)理科に関わる子どもの興味・関心への対応
- 3.家庭における理科・科学に関わる活動の取り組み
- (1)理科・科学に関わる活動の取り組み状況
- (2)家庭の特性と理科・科学に関わる活動の機会
- おわりに
- »第3章 どのような子どもが理科を好きになるのか
- はじめに
- 1.「理科好き」を伸ばす子どもの性格・行動特性
- (1)「理科好き」な子は、どのような性格・行動特性を持っているか?
- (2)「理科好き」の資質とは?
- (3)「理科好き」な子は、理科の勉強も得意?
- (4)理科が好きな子は、どんな教科が好き?
- 2.どのような環境が子どもの「理科好き」を育むのか?
- (1)都会に住む子より、地方に住む子のほうが「理科好き」?
- (2)どのような地域特性が、子どもの「理科好き」を支えるのか
- 3.子どもの「理科好き」を支える、家族のかかわり方
- (1)子どもの理科的な興味・関心に理解を示す大人の家族の存在
- (2)子どもの理科的な興味・関心に対する、大人の家族のつきあい方
- おわりに
- »おわりに